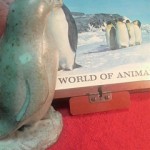ペンギン学の世界には、何人ものビッグネームがいる。すでにご紹介した、G.G.シンプソンやR.T.ピーターソンは、その一例。ほぼ同時代の研究者では、L.E.リッチデイル(やや古い)やW.J.L.スレイドン等がそうだ。彼らの著作についても、いずれ近い内に触れなければならない。
しかし、今回は、ここまでに何回も登場した、ストーンハウスの著書について眺めていこう。
 1988年8月、ニュージーランド、ダニーデンのオタゴ大学で、第1回国際ペンギン会議が開かれた。世界初の「ペンギンに関する国際学会」である。ストーンハウスは、その基調講演の中で、自ら編纂した「The Biology of Penguins」(1975年刊)について、こう述べている。
1988年8月、ニュージーランド、ダニーデンのオタゴ大学で、第1回国際ペンギン会議が開かれた。世界初の「ペンギンに関する国際学会」である。ストーンハウスは、その基調講演の中で、自ら編纂した「The Biology of Penguins」(1975年刊)について、こう述べている。
「『ペンギンの生物学』は、もう絶版になってから久しく、ほとんどコレクターしか関心を示さない本になってしまいましたが、客観的に見て、第二次世界大戦後の30年間に達成された主な業績を、最も要領よくまとめた文献だと言っていいでしょう。」
ストーンハウスは、1950〜70年代初期に多くの業績を残した研究者約40人に呼びかけ、「ペンギン研究の現状と成果」をまとめようとしたのだ。最終的に、30人がその呼びかけに応じ、21編の論文を寄せた。
その顔ぶれは、まさに当時の「ペンギン研究オールスターキャスト」といった感じ。例えば、シンプソン、ボースマ、エインリー、ジョバンタン、クーイマン、ミュラーシュバルツ、ウォーハム等。やがて、ここで一度は著書を紹介することになる人物ばかりなのだ。ただ、残念なことに、日本人の名前は1人もない。
この本の冒頭で、ストーンハウスは、当時の「ペンギン生物学の現状」を概観している。現生18種を属毎にまとめて紹介し、各種の基本データを一覧表にまとめた。また、進化、研究活動の傾向にも触れている。
しかし、より重要なのは、「長期個体数変動」、「飼育下個体群」、「低緯度の種」等に関する研究を網羅することができなかったことに、素直に言及していることだ。
この真摯な姿勢が、後に「第1回国際ペンギン会議」の開催に結実するのである。『ペンギンの生物学』(1975)でやり残した宿題は、1988年に果たされた。この国際学会での大きなテーマの1つは「ペンギンの保全と地球環境の変化」だったが、「1975年の宿題」は、まさに、そのテーマに直接つながる中心的研究分野だったからだ。
ちなみに、第1回国際ペンギン会議の結果をまとめた文献のタイトルが「Penguin Biology」(1990年刊)となったのには、そのような事情があったからだ。この文献については、いずれ見ていくことになる。
さて、ストーンハウスには、他にもいくつもペンギン本がある。あと2冊だけ、紹介しておきたい。
1つは、シンプソンにあの一言「小さな女の子が読むペンギンの本」と言わしめた書籍だ。「Penguins 〜The World of Animals〜」(1968年刊)がそれ。その標題の下にストーンハウスはこんなことを書いている。
「この本を出版するきっかけは、ある小さなアメリカの女の子が、図書館に私の古いペンギンの本を返却する時に、こんな感想を寄せてくれたからです。『この本は私がペンギンについて知りたいと思った以上のことを教えてくれました。』それから10年後、私はこの本を書いたんです。」
この本はまた、ストーンハウスのペンギン観の微妙な変化を知る上でも興味深い。例えば、ペンギンの分類について。ここでは、コガタペンギンを4種、ジェンツーペンギンを2種としているので、全体としては、21種となる。
ちなみに7年後に書いた『ペンギンの生物学』では、18種、この後紹介するビジュアル本(2000年刊)では、かなり慎重にこう記している。
「ペンギンは海鳥です。18種(species)、あるいは種類(kinds)、に分類されています。」
また、注目すべきことに、やはり、フンボルトペンギンについては、野生の映像が全く掲載されていない。この状況は、1975年になっても、そして、驚くべきことに2000年になっても、変わらないのだ。フンボルトの野生の姿がなぜ掲載されないできたのか?その謎については、場所を改めて考えてみたい。
さて、ストーンハウスの3冊目は、ビジュアル本である。「A Visual Introduction to Penguins」(2000年刊)。「Animal Watch」シリーズの1つ。多くの新しい写真と、マーティン・カムの描く、素晴らしいイラストで構成されている。「子ども向きの図鑑」となめてはいけない。人間との関係史から保全、環境問題まで、かなり専門性の高い内容が、わかりやすくまとめられた好著である。
今回はストーンハウスの著書の内、3冊だけに的を絞って概観した。ストーンハウス自身については、その人柄や業績を、改めて「ペンギン史外伝」で紹介していくつもりである。